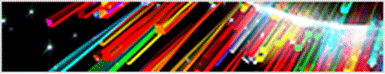「魔法使いプリキュア!」EDでのUnity映像表現の詳細解説~「Unite 2017 Tokyo 」講演レポートその1~(前編)
去る2017年5月8日~9日に行われた国内最大のUnityカンファレンスイベント「Unite 2017 Tokyo 」。ここでは同イベントで行われた66の講演のうち、いくつか紹介していきたい。
今回紹介するのは、1948年に設立された日本におけるアニメーション制作会社の草分け「東映アニメーション株式会社」のデジタル部がおこなった講演だ。登壇したのは、同社でアニメーションディレクターを務める小林真理氏、CGデザイナーの松本八希氏、テクニカルディレクターの中谷純也氏の3名。人気TVアニメーション『魔法つかいプリキュア!』の後期ED(エンディング)映像から初めて使用することとなったUnityの映像表現について、詳細な解説をおこなっていた。
Unity導入により制作コストのカットとワークフローの短縮を実現
同講演で最初に登壇したのは、アニメーションディレクターの小林真理氏。まずは2004年から放映が開始された同社の人気TVアニメーション『プリキュア!』シリーズの紹介からスタートした。
「『プリキュア!』シリーズは当初、手描きのアニメーションとしてスタートしましたが、2009~2010年に放映された『フレッシュプリキュア!』以降、ED映像では3DCGによるキャラクターがEDテーマに合わせてダンスを披露する内容になっています。それは長らくAutodeskのMayaを使って制作してきましたが、2016~2017年放映の『魔法つかいプリキュア!』後期ED映像で初めてUnityを導入してリアルタイムCGの制作をおこないました」
『魔法つかいプリキュア!』でUnityを導入するにあたっては、以下の4点を目標に制作をおこなっていったという。
1.ゲームエンジンのプレビュー画面のクオリティ向上が映像に与えるメリットを探っていく
2.映像制作におけるレンダリング工程のコスト(時間、制作環境)を低減する
3.週替わりのエンディングを提供することで長期番組への話題提供をする
4.Unityを使用してED映像を制作することで今後のVR/ARコンテンツ開発への実験へとつなげたい
また、Unityの導入によりワークフローの改善も目指した。従来のED映像では、MayaとAfter Effectsを組み合わせてカットごとに制作を行っていたがレンダリングに時間がかかっていたという。1枚の素材に1分近くかかっていてそれを12種類ぐらいレンダリングしたのを合成していたため、プリキュア1人/1フレーム平均が「57秒×12素材」=およそ12分が必要。それをレンダリングしデザイナーがコンポジットしてカットを仕上げていくので、1カットあたり1.8作業日かかっていた。
ところがUnityを導入後はブレークダウンの段階でかなり画を作り込んでいたので仕上げのときには少しカラコレするぐらいという形で済み、プリキュア+BG/1フレーム平均「5秒×3素材」=15秒程度しかかからなくなった。その結果、1カットあたり0.2作業日程度で済むようになり、UnityキャプチャーとMayaレンダリングを比較すると、1フレームあたり平均で15秒対12分。Unityを使うことにより48倍(東映アニメーション比)も効率が上がったという。
「Unityを使うことで制作スピードだけが速くなったという話だけではありません。従来はED映像を制作する場合、1本の映像のためにもの凄いすごいコストをかけていたため、それを半年間一方的に流して楽しんでもらうというコンテンツでした。それがUnityのリアルタイムCGを導入することによって1本あたりの制作時間もコストも削減ができ、いくつものED映像のバリエーションを制作することが可能となりました。これにより制作した映像をVR/ARコンテンツに展開するというだけでなく、これまでとは異なるアニメーションと視聴者との関係性ができるかなという可能性を感じることができました」
CGデザイナーがシェーダを自作する意義とは
続いて登壇したのは、CGデザイナーの松本八希氏。Unity用に自作をしたシェーダ「Hakkinen Shader」の解説をおこなった。『魔法つかいプリキュア!』の後期ED映像を制作するにあたり、キャラクターや背景に対し、単一のシェーダでさまざまなマテリアル表現をおこないたいと考え自作することにしたという。
「Hakkinen Shaderではテクスチャおよび単色で指定できるようにしてあり、それぞれの透明度や位置なども細かく設定できるようにしてあります。また、オブジェクトからオブジェクトへと影を落とし、他のオブジェクトからの影を受けることができる『落影/受け影』には、顔などのように影が落ちてほしくない部分など特定部位への影響を白黒マスクによりキャンセルできる機能を搭載しています。そのほか、線色と線幅に加えてカメラの焦点距離に応じた太さのラインを設定できる機能である『輪郭線』や、発光のニュアンスを調整できる『リムライト』『ハイライト』、Y方向のグラデーションをかけられる『Yグラデーション』などといった機能も実装しました」
シェーダを開発するのはUnity映像制作の今回が初めてだったが、そのシェーダ開発を通じてプリレンダーやゲームエンジンの違いを松本氏は実感したという。UnityによるリアルタイムCGでは、シェーダやライトといったパラメータを変えるとプレビュー画像がリアルタイムで変化するためストレスなく作業できた。その一方、さまざまな素材を合成するコンポジットの工程をシェーダで行うため、細かなパラメータが必要であるとも感じたと話した。
最後に松本氏は次のように語って話を締めくくった。
「デザイナーがシェーダを書くという重要性を感じました。シェーダを書くこと自体の敷居が低くなっているということもありますが、デザイナーが欲しい機能を本人で実装できるというメリットが大きいと思います。また、通常のDCC(Digital Content Creation)ツールのマテリアル表現よりも自由度が高いため、将来的にはまったく斬新な表現手法が生まれるかもしれない可能性を秘めているといえるでしょう」
(後編)に続く