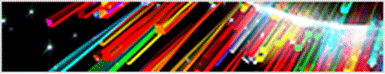国内最大のUnity開発者イベントレポート ~「Unite 2017 Tokyo 」~(後編)
去る2017年5月8日~9日、東京において国内最大のUnityカンファレンスイベント「Unite 2017 Tokyo」が開催された。2017年は会場を東京国際フォーラム(有楽町)へと移し、2日間で延べ6,000名規模の来場者を迎えるイベントとなった。
本イベントへは、Unity本社からゲームエンジンを開発している精鋭スタッフが来日。Unityの最新機能解説をはじめとした講演がおこなわれたほか、様々なゲーム開発者や開発メーカー、ゲームデザイナー、さらにはVR/AR開発者や研究者による66の講演がおこなわれた。
同時に、会場内には展示ブースエリアが開設。ゲームのみならず、幅広い業界からUnityに関わりのある企業が出展し、Unity開発者業界の最先端を体感できるイベントとなっていた。
(中編)より続く
Unity5.6で追加されたグラフィックス関連ツール
大前広樹氏に引き続き、Unity黎明期からエンジン開発の技術ディレクターとして活躍しているLucas Meijer氏が登壇。Unity5.6のテクノロジーに関する講演がスタートした。
まず、紹介されたのはUnity5.6の新機能であるライトエクスプローラだ。この機能はシーン内のすべてのライトの情報を一望できるツールで、そこからライトの状態を変更できるようになっている。
「表示されたデモではすべてのライトが「Baked」になっていますが、『Bake』『Mixed』『Realtime』という3つのドロップダウンメニューからライティングを選ぶことができます。そこでライトを『Realtime』に変更すれば光源は動的に扱うことができます。しかしこのモードは負荷も高くなります。そこでUnity5.6から追加された、『Bake』と「Realtime」の中間となる新モード『Mixed』を使ってみましょう。そうすれば、通常の陰影は焼き込みで処理しつつ、動的な物体にはリアルタイムの影を落とすといった複合処理ができます」
また、Unity5.6の新たなツール「プログレッシブライトマッパー」についても紹介された。このツールを使えば、ライトの色を変えると、ほぼ瞬時に画面のライトマップが更新される。ライト変更終了後には画面の色はすぐ変わるが、細かい部分は「プログレッシブ」」と名付けられているとおり、徐々に変化していく。
そして再度、大前氏が登壇。2017年におこなわれたUnityとMARZA ANIMATION PLANETにおけるジョイントプロジェクト『THE GIFT』が紹介された。
「Unityというゲームエンジンを使用してどこまでの映像表現が可能なのか。たとえば、ハリウッドのCG映像にどこまで迫ることができるかについてチャレンジしようと制作されたのが『THE GIFT』という短編映画です。Unityを使ってGPUでレンダリングをして制作するという取り組みでしたが、『THE GIFT』は単なるテクニカルデモではありません。事実、YouTubeなどの動画共有サイトで600万回を超えて再生されたほか、多くの海外の映画祭で上映され多くの賞を得ています。そこで次に、『Unityのカットシーンエディタ『Timeline』を使って完全なリアルタイムに挑戦してみませんか?』とMARZA ANIMATION PLANETに持ちかけ、実現したのが『Ultimate Bowl 2017』です。この試みにより、『Timeline』でリアルタイムにアニメーションを配置していき、自由に、インタラクティブに、カットシーンを制作していくことが可能なことがわかりました」
『Timeline』を使ってカットシーンを制作するにあたり、Unityでは今後、さらに魅力的な機能を搭載する予定だという。その機能についてはLucas氏にバトンタッチされ説明が続けられた。
「映画業界もゲーム業界も共通の課題はカメラです。カメラワークをどのように設定するのか、そしてどのようにアニメーションとして変更していくかという問題が残っています。そこでUnity2017.1では、Cinemachineと呼んでいるプロシージャルカメラを搭載する予定です。無償で提供されているAdamデモのアセットを使って説明しましょう。Adamデモで3体のロボットキャラクターが単に歩いているだけのつまらないシーンを、カメラワークを変えるだけでワクワクするシーンへと簡単に変化します。それは『Timeline』上に複数のカメラ設定を割り当て、それに従ってカメラワークを切り替えていけばいいわけです。2つのカメラ位置の補間も可能となっており、サイドから背後にかけての回り込みなども簡単に指定できます」
Cinemachineでもっとも興味深いのは、状況対応型のカメラ切り替えのシステムだ。カットシーンではゲーム進行からシームレスに移行するため、ゲーム中の行動で地形やオブジェクトデータがどのような状態になっているか判断できない。そこで影響を受けにくいカメラを指定しておけばCinemachineが自動的に判断。指定のカメラ位置だと支障がある部分だけを切り替えてくれる。
パワーアップしたUnityの2D機能
Unity 5.6では2D機能も多くのアップデートが加えられている。そこでUnity 2DチームのプロダクトマネージャーであるRustum Scammell氏が登壇。数多くの2D新機能を簡単に紹介していった。
「Unityにとって2Dは新しいものではなく、現在、Unityで提供している2D機能は何度も改善されてきました。また、多くのゲーム開発者からのフィードバックによって基本的な2Dのフィーチャーにフォーカスを当てており、Unity5.6では数多くの2Dの新機能を搭載しています」
最後に大前氏が再度登壇。「今回のUniteではUnityが作っている様々なテクノロジーについて学べるセッションを数多く用意しました。その中のいくつかはエクスペリメンタルと呼ばれる実験的な未来のテクノロジーも含まれています。それは実験的なテクノロジーなので将来変更することもあるかもしれません。しかし、今から学んでおくことで半年後、1年後のゲーム開発で新しいプロジェクトがスタートしたとき、あるいは自分たちの作るゲームにもっと素晴らしい体験を提供したいといったとき、必ず役に立つテクノロジーとなるでしょう」という言葉を残し、基調講演が閉幕した。
VR/AR関連の展示や体験が目立った出展ブース
Unityカンファレンスイベント会場内では講演のほか、多数の企業が出展するブースエリアも開設された、ブースエリアは、「第1ブースエリア」と「第2ブースエリア」に分かれて設置されており、「第1ブースエリア」ではボーンデジタルがプロジェクト管理ツール「Autodesk SHOTGUN」や定番のDCCツール「MAYA」「3ds Max」など、コンテンツ作成には欠かせないツールを展示していたほか、様々なゲームメーカーやITベンダーなどが出展していた。
その中には、Unity for Nintendo Switchタイトルの試遊をおこなっていた任天堂や、「HoloLens」の体験コーナーを設けていたMicrosoft、VR/ARデバイスを試すことができるGoogle、VRに最適なGPU「NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ」と、リアルな映像・音響・物理を実現してVRの実在感を高めるSDK「NVIDIA VRWorks」を展示していたNVIDIAなどといった企業も見られた。
また「第2ブースエリア」ではゲームを中心とした体験型ブースが多く出展されており、広大な街を駆け巡るマルチプレイ型VRレーシングゲーム『エアモンキー』(サイバーエージェント)、GoogleのTango技術を使ったゲーム玩具『snipAR(スナイパー)』(ワン・トゥー・テン・ドライブ)、『魔法使いプリキュア!』のエンディング用に制作されたUnityパートをVR HMD「Oculus Rift」で視聴できるコンテンツなどが人気を呼んでいた。
全体を通して、VR/AR関連のコンテンツやハードウェアの展示や体験が目立っていたのが印象的だった。