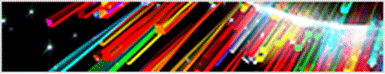「MURO’S VR WORKSHOP」レポート(中編)
(前編から続く)
遊びながらアニメが作成できる『PlayAniMaker』
もう一つのVRツール『PlayAniMaker』は、「遊びながらアニメを作る」をコンセプトに作られた。MuRo氏は、もともとVRのアニメーションを作りたいと考えており、「日本のアニメーションは素晴らしいものがあります。そこでVRアニメーションでも日本のは凄いと思われるようなものを作りたいと考え発表しました」と話す。
MuRo氏は2015年頃からいろいろと試行錯誤していたが、2017年1月に今の『PlayAniMaker』の原型となる「自分で動かして遊べるアニメフィギュアみたいなもの」がコードとして完成。2017年5月には細かいところまで調整して『PlayAniMaker』として配布できるようになった。
「『PlayAniMaker』の機能として、直感的なポージング操作が代表として挙げられます。この機能は3DCGソフトを使わずにフィギュアを遊ぶ感覚でポーズを作れる、というところが魅力のポイントです。たとえば、指先はモーションを作るのが大変ですが、それを直感的に作れるという特徴があります。また、写真を撮るようなスナップショット機能を搭載しており、連続して撮影することでクレイアニメのようなコマ撮りも可能です。あとはキャラクターを使用して、今流行の“ヴァーチャルYouTuber”のようなこともできます」
『PlayAniMaker』のプロモーション動画
『PlayAniMaker』は現在、クローズドで配布されており、ユーザーが作品を制作してTwitterにアップされている。そこではMuRo氏が想像していた以上にさまざまな組み合わせをしていたり、写真をミックスさせていたりなど楽しい作品が数多くつくられているという。
実体験から得た、VRコンテンツ制作時のセオリーとタブー
次に、MuRo氏がVRコンテンツを作成していて体感として学んだことや、現場に生きる小技をまとめた内容の紹介がなされた。
「まず予測と結果についてです。現実とVR内とのイメージを合わせることが大事です。たとえば、本の端を掴んで持ち上げようとしたのに、中心を掴んだような動きをするとプレイヤーは混乱します。そうなるとVRへの没入感が減ってしまうので気をつける必要があります。また、ボタンを押して何かが起こりそうなのに何も起こらないなど、求めていたインタラクションに対して予想していた答えと合致しないインタラクションは没入感を下げてしまいます。僕が体験してきたVRの中にはこういうことがよくありました。逆に、持てないと思っていたのに持てるとか、想像していた以上に触れるとか、そのようなことがあると、逆にワクワク感が増します。そんなインタラクションなら入れてあげてもいいのではないでしょうか」
そして、存在感についてであるが、体験者を置いてけぼりにしないようにすることが大事である。そこで、プレイヤーの行動で物語が進行するなど、プレイヤーをトリガーにする必要がある。また、VR空間は採寸が大事であり、3DCGの場合には背景を大きくして密度を上げるという手法もあるが、それをVR空間で行ってしまうと遠近感が壊れる。そのあたりはきちんと採寸を決めて配置していったほうがいい。
「VR空間では間合いも重要です。体験者から30cmの距離にあるものは掴める距離で、50cmは手を出したくなる距離。60cmは立体感を強く感じる距離であり、1m~1.5mは近づいてみたいと思う距離。2m以上になると立体感は弱くなり背景として認識される距離になります。そこで、60cm以内の距離感には、掴めるオブジェクトしか配置しないような設計にしておく必要があります。舞台設定も重要です。自分の知っている場所や状況では、役を演じようとしやすくなります。ただ、着席していて前方に教師がいたら、設定がなくても「僕は生徒なんだ」と無意識にイメージします。逆に、SF的な誰も知らないような設定にした場合には、舞台設定を担保する必要があります。でないと、ここで自分は何をすればいいのだろうとパニクってしまう原因となります」
(後編に続く)